
|

|

|

|
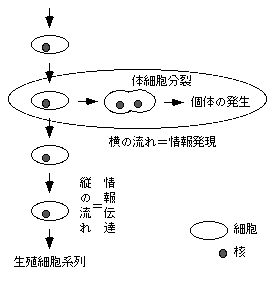 生命現象には2つの情報の流れがあります。ひとつは個体(親)から個体(子)へと伝えられる情報の流れで、もうひとつは個体を発生から分化・老化、そして死へと導く情報の流れです。遺伝とは、もちろん親から子に何かが伝えられることです。そして、子はその何かをもとに成長して親になり、また子をつくります。この何かを遺伝情報と呼ぶことにしましょう。遺伝情報には個体から個体への情報伝達の側面と、そこに書かれたプログラムをもとに個体を生から死に導く情報発現の側面があるわけです。この2つの情報の流れが、生命の起源を出発点とし、生物種の進化をもたらしてきたと考えられます。
生命現象には2つの情報の流れがあります。ひとつは個体(親)から個体(子)へと伝えられる情報の流れで、もうひとつは個体を発生から分化・老化、そして死へと導く情報の流れです。遺伝とは、もちろん親から子に何かが伝えられることです。そして、子はその何かをもとに成長して親になり、また子をつくります。この何かを遺伝情報と呼ぶことにしましょう。遺伝情報には個体から個体への情報伝達の側面と、そこに書かれたプログラムをもとに個体を生から死に導く情報発現の側面があるわけです。この2つの情報の流れが、生命の起源を出発点とし、生物種の進化をもたらしてきたと考えられます。
親から子に伝えられるさまざまな遺伝形質(特徴)が独立の因子で規定されているという概念は、19世紀後半にメンデル(Gregor J. Mendel)によるエンドウの交雑実験で確立しました。それに遺伝子(gene)と名前がついたのは20世紀初頭のことです。19世紀後半には、メンデルの法則に代表される遺伝学だけでなく、細胞生物学も始まり、遺伝に関連した物質が染色体(chromosome)に存在することが見いだされました。そして、これも20世紀になって、染色体の全体(正確には半数体の染色体の全体)をゲノム(genome)と呼ぶようになりました。今ではより概念的に、ゲノムとは、ある生物がもつ遺伝情報の全体として定義されます。ゲノムのなかで生命活動を維持するための機能的な部品を規定しているところが遺伝子です。生命現象の2つの情報の流れのなかで、ゲノムは遺伝情報伝達の単位であり、遺伝子は遺伝情報発現の単位だとも言えるでしょう。
| ゲノム | 遺伝子 | |
|---|---|---|
| 定義 | 遺伝情報伝達の単位 | 遺伝情報発現の単位 |
| 分子のメカニズム | DNAの複製 | RNAへの転写 タンパク質への翻訳 |
| 細胞のメカニズム | 生殖細胞系列 | 体細胞分裂 |